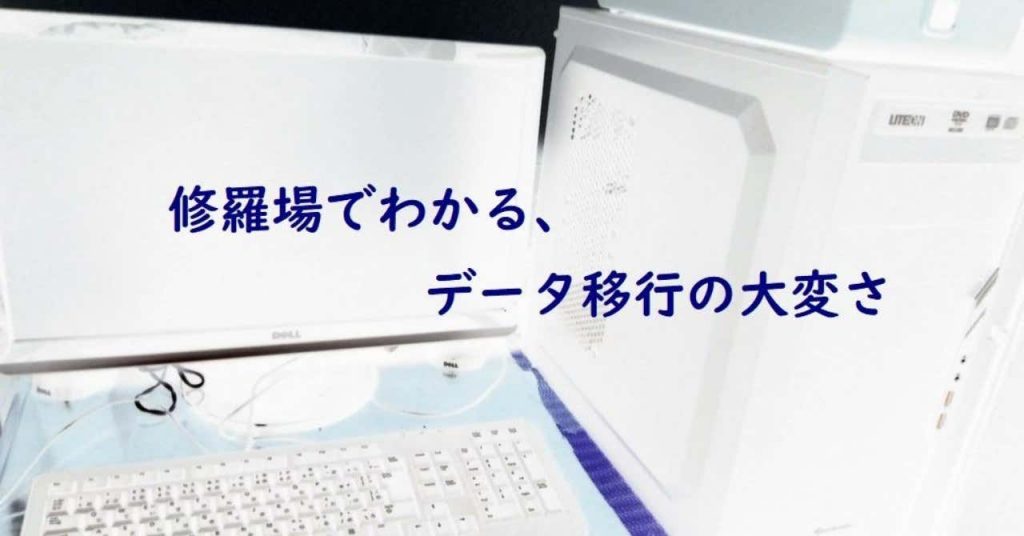「大丈夫、あなたなら絶対にできる。」
隣に座った彼女―偶々、バーで出会った、自分と似た女性―に、云う。
「自分が選んだことに、自信を持って、信じる。自分が信じてあげれば、絶対、大丈夫。」
************************************************************
夕方頃に入ったいつものバーは、いつもの時間にいつもの常連客が来て、いつものように流れていく。
私もその中の一人。その場を構成する一人だった。
毎週水曜日、週の半ばの17時を少し回った頃にこのバーに来て、赤ワインとチーズを頼み、あとは気分に任せながら一人飲む。店を後にする時間は大抵閉店間際。金曜日より人が少なく、私は木曜休み。時間を気にせずに飲めるこの水曜日は、私にとって特別なものだ。
今日も17時を少し回った頃にバーに入り、既に顔馴染みとなっているマスターに目礼をし、そのままいつもの、と言ってカウンターに座る。しばらくそうして一人飲んでいたのだが、今日は酒の進みが早かった。久々に楽しいと思える仕事が終わり、気分がよかった。そうして上機嫌で飲み続け、ああ、今日はちょっと酔いが早く回ったから閉店間際になる前に帰ろうかと考え始めたときだった。
「キール、ください。」
若い女性が隣の席に座った。店を何気なく見渡せばいつの間にか混雑していて、他に一人席は空いていないように見えた。自分の世界に浸っていたから気が付かなかったが、店の中も珍しく騒がしい。
「お嬢さん、若いのに一人で飲むの?」
酔いに任せ、隣の席に座った彼女をさっと観察する。上は白のブラウス、下は黒のパンツスーツに黒のパンプスを履いている。線が細く、どこか儚そうな印象を受ける。黒髪のロングストレートに少し疲れた顔色が見えたような気がした。
「え、あ、はい。」
彼女は驚いてこちらを向く。
「初めて、なんですけど。」
その顔に、私は驚いた。
「あ、えと、だ、大丈夫ですか?」
突然酒に噎せた私に、彼女はおどおどしながらも気遣いの言葉をかけてくる。それを私は手で制しながら、上目に彼女を盗み見た。
―どういうことだろうか。
この娘、若い頃の私に、とても似ている―。
酒の錯覚だろうか?自分の若い頃のドッペルゲンガーが目の前に現れたとでもいうのだろうか。
「あ、あの…?」
彼女が問い返して来て、私は彼女を無遠慮に眺めてしまっていたことに気付く。
「ああ、ごめんなさい。」
姿勢を正し、彼女に向き直る。
「若い頃の私に似ていたものだから、つい。」
「あ、そうなんですか。それは驚きますね。」
正直な理由を述べたものの、彼女は特に気を悪くした様子もなさそうだった。
「で、お嬢さんは一人で飲むんだよね。」
「はい。」
「だったらさ、ちょっと私と一緒に飲まない?」
「え…」
こんなに若いお嬢さんが、本当に一人で飲む気だったのだろうか。一人で飲み屋に来たら何かのハプニングの一つも期待すると思うのだが、そうではなかったようだ。
「隣に座ったのも何かの縁だよ。」
「では…ご迷惑でなければ。」
「ありがとうね。」
会話の区切りを見ていたのか、ボーイが彼女の頼んだキールを置いていく。
「なんの仕事してるの?」
「プログラマーです。」
「お、何系の?」
「Web系?です。サイトを作ったり、作る仕組みを作っているような…」
「奇遇だね、私もそんなものだよ。」
「え?」
「フリーランス、だけどね。PHPっていう言語を主に使って、業務のシステムやサイトのシステム側を構築するような仕事。」
「そうなんですね!」
共通点を見つけたのか、彼女がこちらに興味を持ってくれたようだ。自分の若い頃に似た彼女と自分の職種が同じだというのは、運命とやらを感じずにはいられない。
「でもフリーランス…って何ですか?」
「知らないの?」
「…はい。」
まずい、といった表情で彼女は俯き、運ばれてきていたキールを口にした。この娘は感情が表情に出やすいなと思いつつ、それもまた自分そっくりだと思う。
ゆっくりとシードルを口につけ、軽く一口飲む。じんわりとアルコールの熱とでもいうのか、が胸に溶けていくのを感じながら、私は口を開いた。
「そんなにまずそうな顔しなくていい。フリーランスっていうのは、言ってみれば一人自営業さ。個人事業主、とも言うね。聞いたことある?」
「自営業、は聞いたことあります。」
「そう、つまりはそういうこと。」
「派遣とは違うんですよね?」
「まあ、派遣みたいな働き方のフリーランスもいることはいるけれど、私はそれは性に合わないからやっていないね。」
彼女は小首を傾げて考え込んでしまう。正面を向いてキールを口に運んでいる。つまみがないので、こちらで頼んでいたウインナーの盛り合わせを彼女の近くに置いた。
「どうぞ。」
「え、いいんですか。」
「付き合ってくれているお礼だと思って。」
「じゃあ…ありがとうございます。」
「アルコールばかり入れるんじゃないよ?」
軽く頭を下げ、彼女はウインナーを口に運ぶ。
「あ、美味しい。」
「そうだろう。ここはつまみも中々美味しいからね。つい飲んで食べすぎてしまう。」
そういったところで私もシードルを口につけ、小さめのウインナーを頬張る。
「あなたは、会社員のエンジニアさんかな?」
「はい、そうです。」
「何年目?」
「一年目です。」
「へえ、じゃあまだ始まったばかりか。ゴールデンウィーク明け、出社が嫌にならなかった?」
「ま、まあ、何とか。」
曖昧に返事をしながら、彼女は視線を泳がせた。なんと応えたものか、というところだろうか。
「何とか出社した、っていうのでも出社したのなら、偉いね。そこも一つの壁みたいなものだから。」
「別の部署では来なくなった人もいました…」
「あらま。」
「でも…実は…私も、行くの辞めちゃおうかな、って思ったんです。」
キールを両手に囲みながら、彼女は寂しそうな目でグラスの水面に視線を移した。
「私、文系卒で。プログラムの勉強とか、全然してこなかったんです。授業にも当然ないし。同期はいなくて私だけなんですけど、周りで同じような境遇の人がいなくて…しかも、女は私だけだから、何となくやり辛くて…」
行きずりの飲み相手だからだろうか。それとも早くも酔いが回ったのだろうか。それか、相当参っているのか。
自分も会社員をやっていた頃、相当参っていた時期があったなと漠然と思い出す。10年も前になると遥か彼方の出来事のようだが、確かそれは彼女と同じ、丁度5月過ぎくらいだったと思う。
「わかってたんですけどね、4月のお給料が本当に少なくて。15日締めの25日払いで、2週間も働いていないから、予定月収の半分くらいになること、わかっていたんですけど、それもなんだかな、ゴールデンウィークがあったのに全然遊べなかったな、って思って。」
「ああ、新しく入って1か月目はそうなるよね。」
フリーランスも相手方の締め日によって支払いが変わることもあるから、その気持ちは今でもわからなくはない。
「大して遊べなくて、それでそのまままた仕事って…私、そんなに強くないのに、この会社でやっていけるのかな、って思うんです。」
「強くない?」
「体、丈夫じゃないんです。周りの先輩たちが午前様上等で働いている中、私はそんなに遅くまで働けないんです。働いたら、次の日ほぼ休みます。でも先輩たちは当たり前のように朝9時に出社してきていて。まあ、毎日午前様ってわけではないですけれど、すごいできる人ほど仕事が集中して遅くなってしまうみたいで。」
「いやあ、それ当たり前じゃないから、できなくても当然だと思うけど…周りがやっていると、自分だけできないのってなんだか嫌だよね。」
「はい、嫌…です。」
私はシードルを飲み干し、次は貴腐ワインを2つ、頼んだ。そのまま皿に残ったウインナーを一切れ齧る。
「私も昔、そんな職場にいたなあ。」
「え…」
「懐かしいね。私もあなたと同じようにそんながむしゃらに働けるようなタイプじゃないから、ちょっと無理をするとすぐ体を壊したよ。残業2時間する日々が続いたらもう半ばには使い物にならないの。」
「わかります、それ。」
「無理するもんじゃないよね。」
「ですね。」
「で、行くの辞めちゃうの?」
「え?」
貴腐ワインを2つ、ボーイが運んできた。それを一つ彼女の方に置き、私はグラスに口を付ける。
「いや、嫌みたいだから、辞めちゃうのかなって思って。」
彼女は少し戸惑いを見せた後、一気に半量以上残っていたキールを飲み干す。そのままグラスをやや荒めに置いて、私に向き直った。
「本音では、辞めたいです。たぶんブラックなので。先輩たち、代休も取れなくて毎日働いているような人もいますし、残業代は出ませんし。」
「うん、ブラックだろうね間違いなく。」
「でも、迷うんです。私、…その、自力で入社できなかったので。」
「は?」
「コネ入社、みたいなものなんです。」
聞けば彼女は現在の会社を親のそのまた友人が勤めていた会社だ、ということで面接してもらい、内定をもらったのだという。
「しかも就職浪人して入っているので、辞め辛いんです、親の手前もあるし…」
彼女はもう一つの貴腐ワインを、いただきます、と小さくいって口を付ける。どうやら口に合ったらしい。
「どこまで似ているんだろうねえ。」
「え?」
「いや、こっちの話。」
彼女に姿だけでなく、経歴も似ていると言ったら、どういう反応をするのだろうか。
「今の仕事、楽しい?」
「え?あ、はい…えっと、プログラム自体は、とても楽しいです。まだまだ全然わかりませんけれど、あの、あなたと同じPHPを使っています。連想配列の概念?がまだ把握できなくて困っていますけれど…楽しい、です。」
「連想配列ね、あれはある日突然道が開けたようにわかるから安心していいよ。それはいいとして、」
ずい、と彼女に身を寄せる。半歩、彼女が後ずさったような気がした。
「仕事が嫌いじゃないなら、続けてみなよ。死なない程度に。」
「そ、それは…。」
「死にたくなることもあるだろう。現に、今日は死にたいと思うようなこと、あったんじゃないの?」
「…!」
図星だったのか、彼女は目を見開き、こちらを見返してくる。
「なんで…」
「そういう表情してたの。あなた、相当に思っていることが顔に出やすいから、気を付けるんだね。」
どこか自分に言い聞かせるように彼女に言う。
「今の仕事が好きなら、今の会社にいた方が何かといい。誰にでも無駄死にしてほしくはないから、私はあなたに頑張れとは言わないけど、プログラムの仕事を続けたいなら、辞めるな。今は辛くても、辛いことがあっても、糧になるから。」
彼女は驚いたように、でも素直にこちらの話に耳を傾けている。私は貴腐ワインをぐいっと飲み干し、その勢いのままに続けた。
「どんな出来事も、全部自分だけが経験できるものだ。どんな過去だって、それは今の自分に全部必要なものなんだよ。私はそう思ってる。」
幼い頃、原因不明の症状で3年近く入院したこと。
結局完治がみられないまま退院し、うまく人間関係を築けないまま、学校で仲間外れにされながら青春時代を送ったこと。
大学デビューしようとしたけれど見事に空回りして、恐らくとても変な人だったこと。
大学院進学しようとして失敗したこと。
就職状況がよくなかったことも相まって就職浪人したこと。
公務員の筆記試験は通っても、面接で必ず落ちたこと。
何を狂ったか、警察官試験を受けて落ちたこと。
ようやく内定をもらって入社した1社が、ブラック企業だったこと。
とにかく経済も情勢も社会のことを知らない、世間知らずで大変苦労したこと。
ブラック企業を結婚して妊娠して退職したこと。
家事はそれなりにできても、憧れの専業主婦が向いていなかったこと。
再就職したこと。
育休を取ったけれど会社を辞めたこと。
それでも今、家族と生きていること。
酔っ払いの舌で、気づけば自分の過去も交えて思い切り話をしていた。
そんな年上の、初めて会った、たまたまバーで隣に座っただけの女性の話を、彼女は驚きながらもただ静かに耳を傾けていた。
「色々嫌なこともあったけど、後悔はしなくなった。全部今の自分がいるために必要なことだったと、思うようになったからね。だからあなたも、今の会社にいて働いていることは、きっと今の自分がいるために必要なことなんだ。」
言葉を切り、居直す。それにつられてか、彼女も居直した。
「大丈夫、あなたなら絶対にできる。」
隣にいる女性―自分とよく似ている―に、云う。
「自分が選んだことに、自信を持って、信じる。自分が信じてあげれば、絶対、大丈夫。」
**********
「…さん、…さん。」
バーのマスターに揺り起こされて、私は目を覚ました。どうやら酔った勢いで、そのままカウンターで寝てしまっていたらしい。
隣にいたはずの、自分にいた彼女は、既にいなくなっていた。
「寝ちゃってたんですね。」
「そうですよ。無茶な飲み方するから…何かあったんですか?まあ、もうそろそろ閉店になるんで、お仕度お願いしますね。」
ちらりと彼女がいた席を覗き見る。カウンターは既に綺麗に片づけられていて、彼女がいた痕跡は跡形もなかった。
―彼女は、過去の新社会人1年目だった私、だったのだろうか。
そうだとしか思えないくらい、彼女と私は似ていた。過去の自分に会った、という表現がぴったりなほどに。
もし過去の私がここに来ていたのだとすれば、彼女は1週間程後で午前様を強いられるデータ移行作業の担当になり、デスクの前で船を漕ぎながら処理の終了を待ち、移行のデータの確認をし、タクシーで帰社する。次の日は1時間ほどの遅刻で出社するものの、丸1日船を漕いで仕事をしたのか寝ていたのかという状態になり、その後2日間は寝込むことになる。
また半年もすれば、彼女は仕事で大きなミスをして、どうしていいかわからずに席にいるだけの状態になる。周りのフォローが全く得られず、2日程針の筵状態でその場にいることになるはずだ。
そうして2年後には付き合っていた彼氏と結婚し、また1年後には妊娠し、出産を理由にしつつ、会社に見切りをつけて退職する。
その後も色々な出来事があり…夫と子供達の支えもあり、フリーランスとして生計を立てることになる。
新社会人となった彼女と同じ頃、自分がフリーランスとして生計を立てていることなど、想像していない。彼女が私なら、彼女もきっと私と同じ思いをすることだろう。Webエンジニアとしての技術をもって、会社員とは全く違う、自由で厳しい世界に身を置いているなんて思いもよらないだろう。
「大丈夫、あなたなら絶対にできる。」
隣にいたであろう彼女に贈るように、小さく呟いた。
「自分が選んだことに、自信を持って、信じる。自分が信じてあげれば、絶対、大丈夫。」
社会に放り出されたばかりの、あの子に届くと良いなと、信じて。