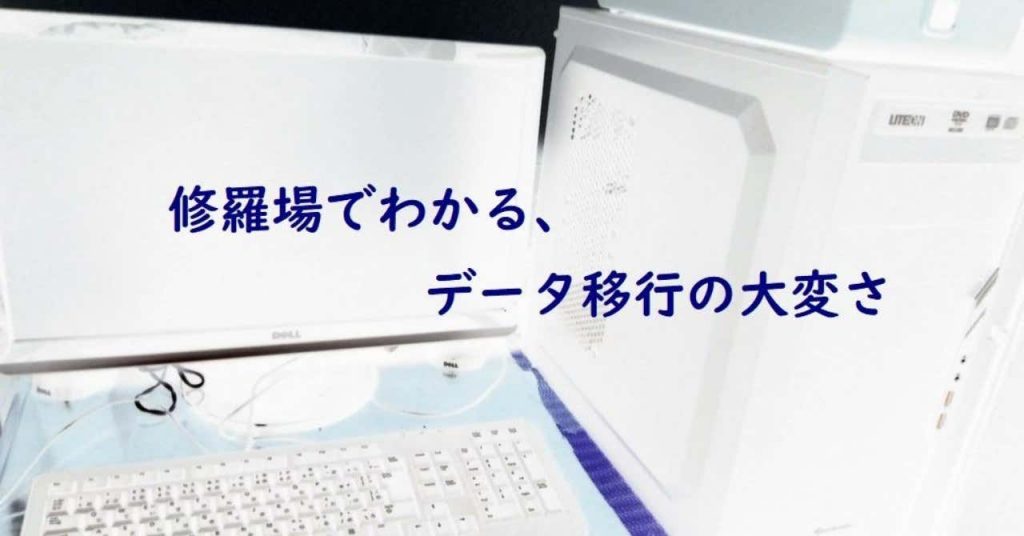少年が公園で見たものは、穴。
少年以外が見たものは、木や、オブジェなど、形は様々である「モノ」のようで、穴ではない。
彼が見たものの正体は?足を踏み入れたその先にあったものとは―?
– あなたが見ているもの、覚えているもの、それはすべて他人と同じと言えるでしょうか? あなたの覚えているものは、本当に正しいことですか?-
―あれは、何だろう。
近所の公園の、少し奥のところに、それはあった。
木々が生い茂る場所。林というには足りず、かといって広場とも言えない。木々がお互いの居心地がいい距離感をもって空に伸びている場所だ。
初めて見かけたときは、そのまま通り過ぎた。夕刻で辺りが薄暗かったこともあり、家路を急いでいたから。
二回目に見かけたときは、昼間だった。夏の暑い日で、熱気による蜃気楼のように、空間が揺らいでいるように見えた。
三回目に見たとき、これはもう偶然ではないなと思った。
奇妙に感じられたのは、自分以外はまるで気づいていないように見えたことだった。
確かに木々が生い茂る場所に、それはあった。
それでも全く人目につかないかというとそうとも言えない。しかし、程近くを通るジョギング中の若者や、日課の散歩をしている老人といった、その辺りを毎日通っているだろう顔ぶれも、全く気づいていないように見えた。それどころか、その近くを通り過ぎるときに「完全に無視している」としか思えない。そこに建物のような障害物があるかのように「避けている」。
顔見知りでもない彼らに自分が「あそこに何があるんですか?」とは到底聞けなかった。ましてや家族にも聞く勇気はなかった。万一自分だけが見えていて、他の誰からもそれが見えていない場合、変人扱いされた挙句に、昨今の精神医学ブームに乗じて精神科に連れていかれてしまうかもしれない。
結局誰にも相談できることなく、ついに四回目に、それを見た。
これは偶然ではない。朝、まだ人がそれほどいない早朝に、家を出てその場所へ「確認しに行った」。
やはり近所の、木々が生い茂っていて目立つ場所ではないが全く目につかないというわけでもない少し奥まったところ。そこにそれはあった。
恐る恐る近づく。
付近を歩いた人が避けていたような、障害物はやはりない。しかし、確かにあった。
半径2kmはありそうな穴が、ぽっかりと空いていた。
淵へ近づき、そっと覗いてみる。
―今住んでいるところとは全く違う、地下の街が広がっていた。
白い建物のようなものが穴の周りをぐるりと埋めるように広がっていた。その建物を飾るかのように、蔓がはびこっている。古い建物のようにも見えるけれど、敢えて蔓をはびこらせている芸術作品のようにも見えた。
霞のような靄がかかっていて、すべてを見渡すことはできなかった。
吸い込まれそうな気がして、一歩下がってみる。
すると、穴の周りに階段のような、狭いけれど足を引っかけて降りていけそうなところが見えた。
この地下の街は何なのか。
自分だけが見えているようなこの穴の先は、何なのか。
好奇心がじわじわと疼きだす。同時に、何があるかわからないところに一人で飛び込むのは危険だという警鐘も響く。
どうするかとしばらく悩んだ。
どのくらい悩んだだろうか。ふと気づくと陽が先ほどよりも上っていて、人がまばらに出てきたようだ。
呆然と穴の前で立ち尽くす自分は見られているのかいないのかわからないが、気に留めている人は皆無のようだった。
この穴の中に入っていくことを見られるのは何となくいけないことのような気がした。名残惜しさを感じながら、地下の街を目に焼き付けて、踵を返した。
そして、改めてこの中へ進むのか、進まないのかを決めることにした。
*************************************************
家に帰ってから、しばらくは先ほどの街のことが頭から離れなかった。
なぜ誰も気づかない、建物か何かがあるような障害物を自然に避けているような動きをするのか。自分だけが見えている様子なのか。
自分だけが見えているのならば、どうして自分は見えるのだろうか。
悶々と同じことを考えてしまう。本を開いて別のことをしてみようとしても、スマートフォンを開いても、結局は同じことを考えていた。
悶々とした日々を過ごした数日後、通学日。
何となく日常を過ごしていたものの、やはりあの公園のあの穴が気になって、身が入らない。授業中も当てられたことに気付くのが遅れたり、体育でボールを顔面から受けてしまったりとお決まりのようなことをやらかしてしまい、クラスメイトに心配された。
それが週の半ばにはひどくなり、教師に「今日はもう帰って休め」と言われてしまった。
「あの、俺も一緒に帰ります。」
心配したクラスメイトの一人と一緒に。
別に具合悪くないからと断ったのだが、意地でも食い下がらないので、こちらが折れる形になった。
「なんか、今週入ってからおかしいよな?お前。」
「うるせー放っておけよ。」
「あんな体を見せておいて、よくそんなこと言えるよな…心配するなって方が無理だぜ。」
学校からの帰り道、並んで歩きながら軽口を叩きあう。その最中でも、自分の頭の中はあの謎の世界のことでいっぱいだった。
「それで」
こほん、と咳払いの後、彼は続けた。
「何があったんだよ?一体。」
「それは…」
言いかけて、やはり言っていいのかどうか考え込んでしまう。
「なんだよ、歯切れ悪ぃな。」
「悪ぃ」
「言っちまったほうが、楽になるんじゃねーの?」
そう言って彼は学生かばんを持ったまま両手を頭の後ろで組んだ。
「言わないと、わかんねーしよ。女でもないんだし。」
学校に通う年齢の、思春期の少年と言えば、考えることは単純だ。気になる女がいて、それに悩んでいるとでも言いたいのだろうか。
ちょっとむっとしながら、おそらく意図とは異なることをわざと答えた。
「女って…そんなわけねーだろ。なんで俺が女なんだよ。」
「なんでお前が女だったことになるんだよ。たとえだよ、た・と・え。大体…」
「わーってるよ」
いい感じに女の話題に入りかけたものをやや強引に逸らし、そのまま喧嘩なのか軽口なのか、を叩きながら歩く。
しばらく行くと、例の公園、-丁度あの場所が見える位置-を通りかかった。
あの出来事を思い出し、つい足を止めてしまった。
「んだよ、急に止まって。」
少し先を行ってしまった彼が、つれねぇな、などと言いながら戻ってくる。
「…おい。」
「ん?」
「あそこに、何が見える?」
「あ?」
訝し気な態度で、彼は自分の指をさした方向を見た。
「何があるってんだ…」
「いいから。」
「…ただの、でっけぇ木。」
「木?」
「おう。それしか見えねぇけど。見てるとこ、違うか?」
恐らく、彼は見ているところを間違えてはいないだろう。自分には、大きな木はまるで見えなかったから。
木は木としてたくさんあるが、「でっけぇ木」と表現するにはまだまだ覚束ない木々ばかりが目に入る。彼は自分の指さしたところを恐らくしっかり、外さずに見ている。
「…そっか。」
「なんかあるのか?」
「いや、別に。」
「なんなんだよお前、本当…なんか、おかしいぜ?」
「知ってる。」
「は?」
彼のそれ以上の問いには答えず、再び歩きだした。
この現象、地面に巨大な穴が空いているものを見てから、他の人にどう見えているか尋ねたのは初めてだ。
尋ねた彼、クラスメイトは「でっけぇ木」と表現した。
そして恐らくそれは、間違えていない。
もしかしたら他の人には木ではないのかもしれないが、目の前に大きなものがある、という認識をしているのだろう。でなければ、皆が皆、あれを「避けている」行動を取るはずがない。
自分には今日も障害物のようなものがあるようには見えず、穴のようなものが広がっているように見えた。そしてそれは、自分にとっては正しいのだろう。
「俺、帰るわ。」
「あたりめーだ。何のための早退だよ。家の中に入るまで見届けるからな。」
「なんの真似だよ、親かよ。」
「なんとでも言えよ。」
* * *
家の中に入り、彼の気配が消えた後。
部屋に戻り、ベッドに体を勢いよく預けた。
あれを、どうしたものか。そればかり考えていた。
中に入ってみたいという好奇心は大いにある。しかし、当然ながら危険もあるだろうと予測できた。なぜならそこは自分以外には見えていないようなので、もし何かがあって穴から叫んだとしても、危険を知らせる声が誰かの耳に入ることはないかもしれない。
そもそも、穴の深さがよくわからない。途中に靄がかかっているように見えて、正確な底は推し量れそうにない。すぐそこかもしれないし、ずっと下にあるかもしれない。
好奇心と、警告と、両方が頭の中を飛び交っていた。
どちらにするべきか。
一時間ほど布団の上でごろごろ転がりながら考えていた。時刻は15時になろうとしていた。
―行くなら、今しかない。
時計の針をぼんやりと眺めていたら唐突にそう思った。理由はわからない。しかし何かがそう言った気がした。
「…よし。行こう。」
勢いよく体を起こし、ベッドから立ち上がる。
制服を脱ぎ、ジーンズとTシャツに着替えた。
それなりの大きさのリュックを手にし、リビングに降りた。
中に飲み物、軽食、上着、軍手、絆創膏、カッターなど、冒険に必要そうなものを詰めた。あくまで持ち歩いて怪しまれない程度の量を詰めていく。
そうしてキャップを目深にかぶり、まだ誰もいない家を出て、玄関の鍵を閉めた。
なんとなく誰かに見つかったらいけないような気がして辺りを見回す。幸い、人通りは少なそうで、自分を気に留める人などいるようには感じられなかった。
何事もないように公園まで歩いていく。まだ下校時間には早い頃だったが、誰かに見つからないようにと祈っていた。誰かに見つかったら、この冒険には行けない気がした。
例の場所までは10分もない距離だったが、恐ろしく長く感じた。悪いことをするときはきっとこんな気分なんだろうなと思った。
今からやることは、別に悪いことでもなんでもないはずだ。「誰にも見えていない領域に侵入する」、これが背徳感を感じさせているのかもしれない。
人もまばらな時間、穴の前についた。先ほどのクラスメイトが言っていたような、大きな木はやはりというべきか、自分には見えなかった。
穴の淵に立つ。見つけた時と同じ、地下の街が広がっていた。
「-行くか。」
ここまできて、悩んでいても仕方がない。
生唾を飲み込み、崖の淵の、足のようやくかかるだろう場所に、一歩踏み出す。
じゃり、と靴と小石が擦れる音がした。
ぱらぱらと砂が穴の下に落ちていくのが見えた。足元が崩れる感覚はない。
大丈夫だろうと踏んで、もう一歩、踏み出した。次の足場はもう少し広く、つま先が乗る程度はあった。
じゃり、じゃり、とゆっくり歩を進めていく。十歩も進むと慣れてきた。足場も少しずつだが、土踏まずを覆うくらい、両足が乗る程度には広がってきた。
穴の上からは見えなかった世界が、少しずつ開けてくる。
高揚感を抑えきれず、一歩、また一歩と、ついには普段と変わらない速度で下り始めた。
足場は穴の周囲をぐるりと回ってた。常に片側に壁がある。手をついて下りればそれほど危険はなさそうなくらいだった。
ふと、視界が白くかすんでいることに気付く。上を見上げると、地上にあっただろう木の葉が辛うじて見えた。
―調子に乗って、下りすぎたか。
歩を止め、上を見ながらしばし考える。しかしここが「下れる場所」で「白くかすんでいる」こと以外は、まだ何もわかっていなかった。
―もっと、探ってみるべきだ。せっかく来たのだから。
そう言い聞かせ、視線を前に戻した。
視界は白くかすんでいるが、何も見えないわけではない。目を凝らしてみると、地上から見た一部の景色、白い建物のようなものと、蔓延る蔓が見えた。
再び壁側に手をつき、一段、また一段と下り始めた。
土を切り裂いたような武骨な壁から、小石が零れ落ちていく。螺旋状になっているのかどうなのか、外壁をぐるぐる回るような形で下っているので、なんだか三半規管がおかしくなってきたような気がする。
またしばらく進むと、ふと、壁側についた手の感触が変わった。
見てみると、土壁がつるつるした材質のものに変わっていた。規則正しい石を積み上げているようだ。レンガの一種なのだろうか。
視線を前に戻すと同時に、ざあっと風が吹いた。それと共にそれまで覆っていた白い霧が晴れていく。まるで、自分の到着を待っていたかのように。
吹き荒れた風が落ち着くころには、遠くまで見渡せるようになっていた。
地上からは見えなかったものがはっきり見えていた。そこには途中でかすんで見えたような、白い建物のようなものとそれに蔓延る蔓がはっきりと見えた。
自分が下りてきた壁側の方は、壁に沿う形で所謂団地のような、長方形の、高さのある四角い形状の建物が並んでいる。それが規則正しく、列を成して建っていた。どこまで続いているのだろう。
手入れをされずに放置されていたこととから外壁が崩れ落ちそうになっている上に、蔓に覆われて建物そのものが埋もれそうな勢いだった。建物の右上辺りに建物の番号を示すものと思われるものが見えた。自分の一番近くの、はっきり見えた番号は「17」だった。
自分が下りてきた方向と反対の方向、右側を見ると、そちらは遠くに数点の、やはり白い建物が見えるだけで、あとは原っぱのように見える。公園らしきものもあるのが伺えた。
「昭和の時代の…団地?」
街並み自体は、社会の教科書の写真に出てきた一場面に似ているように思えた。ただその写真はモノクロだったので、建物の色が全部白だったのかはわからない。
今は昭和を超えて令和の時代になっていて、まだ昭和の時代に建てられたものは残っているが、それらもこんなに白い建物ばかりではなく、どちらかというと味気ない鼠色のコンクリート色の建物が多いと思う。
なんだろうな、過去の遺物っていうやつでもないのかなー
首を捻りながら、下りてきた壁から手を放し、右側―建物とは反対側の、何もない原っぱの方に歩いてみる。
少し歩くと奥の方に左側にあったものと同じような、白い建物が見えた。
こちらも蔓に覆われているようだ。左側から見た建物とは異なり、こちらは低層の建物で、密集していないようだった。ぽつん、ぽつんと建っているように見える。薄い靄がかかっていて、完全には見えない。
一番近い建物に近づいてみことにした。
原っぱは手入れがされているかのようにほぼ規則正しい高さを保っており、時々何かの花びらが舞っていた。どこかに花畑でもあるのだろうか。
―人の気配、生き物の気配すら、一切しないのに。
気づいて、はたと足を止める。
そうだ。こんなに「昭和の時代のものか」と錯覚するようなものがある―明らかに獣だけではなく、人の手が入っている場所にいる。それなのに、「生き物の気配がしない」。
人に捨てられた里はきっとその辺にある山の中のように、所謂自然に戻る。自由に木々が生い茂ったり、原っぱなんてものではなくもっと草が伸び放題になるだろうし、歩きたくなくなるくらい、虫もたくさん飛んでいるだろう。
なのに、なぜこの原っぱは規則正しく、手入れがされているかのような高さを保っているのだろう。
じりと焦りが募った。もしかしたら、俺は相当やばいところに足を踏み入れてしまったのではないか?大体、誰にも見えていないようなところだったし、クラスメイトも木が生えているだけだと言っていた。
ぴたりと足が止まってしまう。まるで何かに囚われてしまったかのように、動かなくなった。
急に喉の渇きを覚え、結構な量の汗が出ていることに気付いた。
再び、ざあっと風が吹いた。少し先に薄くかかっていた靄が、綺麗に晴れた。
「俺を…呼んでいるのか…?」
ごくりと唾を飲む。漫画なんかでよくある表現だけれど、こういう自分がピンチかもしれない状況のときは本当に唾を飲みこむんだな、とまるで別人のように思う。同時に、この先へ行くべきか、戻るべきかを考えていた。
「―進むしか、ないよな。ここまで、来たんだし。戻ろうと思えば、いつでも戻れるさ。」
そんなことを言い聞かせながら、もう一度足を踏み出す。縛り付けられていたような感覚は消え、いつもと変わらない足取りに戻った。
そう歩かないうちに、一番近い建物に着く。所謂一軒家のように見えたが、外壁から屋根から何から何まで白かった。唯一色があったのは、長年放置されていたと思われる、木製のささくれた縁側の台だった。祖母の家にこんな形の、家の外についていた腰掛のような部分があったような気がする。
喉の渇きがひどかったため、そこで一旦休憩を取ることにする。
「あの…すみません、お借りしますねー…」
相変わらず何者の気配も感じないが、一応声をかけてその家の縁側の台にそっと座る。木が軋む音がした。
縁側の台に座り、持ってきた飲み物を出す。ペットボトルを開ける音が、ぱきり、と辺りに響いた。そのまま少し唇を湿らせる程度に含む。
―思っていたよりも、体が水分を欲していたようで、すぐに半分ほど飲み干してしまった。
「いけね」
飲み物はこれとあともう一本入っている。何があるかわからないし、川などの水や水道を発見したわけでもない。民からしいところの周りには水道はないようだ。そもそもこんな誰もいなさそうなところに蛇口はあったとしても、水道が通っているのだろうか?とにかく、持ってきている飲み物を全て飲み干してしまうわけにはいかなかった。
そういえば、今は何時だろう。
長い階段を降りてきた。夢中で降りてきた。降りてから、平面も歩いた。
どのくらい移動したのだろう?そういえばここは陽が高そうな印象を受けるけど、一体何時間くらい過ぎたのだろう。
急いでリュックからスマートフォンを出す。起動ボタンを押してみると、そこには「–:–:–」と表示されていた。加えて、圏外のようだ。
念のため適当に自宅の固定電話にかけてみるが、ツーツー…となるだけでかからない。焦って何回も色々なところにかけてみたが、全くかからなかった。
「俺、これ結構やばいんじゃね…?」
外界から隔離された場所にいると感じ、じりと焦りが募った。
自分の体内の時間間隔を頼りにするなら、最低でも1時間くらいは階段を下っているはずだ。そこから建物を見つけて、ここまでは恐らく30分ほどはあったと思う。
最低でも90分。
だとしたら、現在時刻は恐らく「16時半以降」だ。15時くらいに家を出てきたのだから、そのくらいになっていても不思議はない。
今から急いで引き返したとして、元の場所に戻るのは、現在時刻の予想がほぼ正しかったとして「18時過ぎ」だ。もしかしたらそれよりもずっと後かもしれない。
すぐに戻れば、諸々のことが公にならずに済むはずだ―。
どんどん焦りが募った。階段は下りだったから、上りだと更に時間がかかるかもしれない。お世辞にも体力に自信があるわけではないので、もっと時間がかかってしまうかもしれない。
少しでも体力を補うため、持ってきた小袋のクッキーを1袋、一気に放り込み、飲み込んだ。その上から残っていたペットボトルの水を一気に飲み干す。残りはあと1本だ。
―帰ろう。それしかない。
時既に遅し、となっているかもしれないが、とにかく戻ることにする。
物をしまい、勢いよく縁側の台を立った。台ががたんと大きく揺れた音がした。構わず、そのまま立ち去った。
座っていた縁側の台は、そのままゆっくりと倒れてしまったような音がした。その衝撃音が周りに広がり、いつも以上に大きく響き渡った。
「?なんだ、この音…」
おぉぉぉおぉん…
何かの呻き声のようなものが、遠くから聞こえた。先ほど自分が倒してしまったと思われる縁側の台の音ではなさそうだった。
ここにきて初めて感じる生き物のような声…獣の類だろうか?
―仮に獣がいたのだとしたら、マジでやばいな。
軽い言葉が頭に巡る。そう表現するしかなかった。緊張で手に汗が出てきている。
「!?なんだ、これ!?」
来た道を戻っているはずなのに、先ほどはなかった蔓が目の前を遮る。こんな蔓の壁のようなものなんて、なかったはずだ。
迂回すれば進めるだろうか?急ぎ歩きで蔓の周りを歩いてみるが、どこまでも横に続いていて、前には進めないような気がする。
「仕方ない」
蔓に対して申し訳ない程度の攻撃力しかないだろうカッターを取り出す。
「ないよりマシだ」
手で引きちぎりつつ、どうしても難しいところはカッターで裁断していく。すぐに、自分が通り抜けられる程度の穴が空いた。
すぐさま穴を抜ける。また開けたところに出たが、少し先にもまた蔓の壁が見えた。
「なんだこれ…!?さっきはなかったよな…!?」
誰に問うでもなく、言葉を発する。
誰かが隣にいたら少しは違ったかもしれない。一人で来てしまったことを後悔した。
とりあえず前に進むしかないだろう。相変わらず蔓の切れ目は見えない。
同じように蔓を裁断し、穴を作ってそこから抜け出る。
「またかよ!」
蔓の壁、寸分違わぬ光景が広がる。文句を言いながらも同じように穴を作って抜け出る。何回か繰り返したところで、蔓が途切れた。
肩で息をしながら、呆然と立ち尽くす。
「あんなもん、なかったよな…」
蔓を抜けた先に、廃墟ビルのようなものがそびえたっていた。
「違うところ、来ちまったのか…」
辺りを見回して、そのまま振り返ると、既に蔓はなかった。目を凝らしてみても、あれほど苦労して通ってきた蔓の壁の痕跡が、何もない。自分が切り落としたはずの蔓の一部もない。
蔓に誘導されたのかもしれなかった。
ビルは10階建て程度の低層で、一棟だけ。周りには何もない。ビルの周りに原っぱ。あまりに不自然だった。
迂回していこうと思えば行けそうだった。廃墟に入る趣味はないので、ビルを無視して階段を探すことにする。
一体、下ってきたあの階段はどこにあるのだろう。
しばらく歩くと、また、廃墟ビルがあった。同じように無視して歩いていく。
「またかよ!」
いくらか進むと、同じ廃墟ビル、原っぱのところへたどり着く。
「ループしてんじゃねぇの、これ…」
徒労に終わっているのではないか、自分は何者かに延々と同じところを歩かされているような気がしてくる。
「どうあっても、入れってことかよ」
明らかに人がいないだろう建物に入るのは、何となく怖い感じがした。正直言と、入りたくない。
「あ、でも…そうか、ビルの屋上に出たら、何か見えるかもしれない…よな。」
原っぱに座り込み、しばし考える。仰向けに寝転ぶと、靄がかかった青味の空が見えた。―空のように見えるだけかもしれないが。
「!」
しゅるしゅると音がした。
何事かと身を起こしてさっと辺りを見渡すと、蔓が勝手に動き、自分とビルを覆いつくすように周囲を周っている。
「ゲームか何かかよ…!」
そのまま座っていると蔓に巻き込まれてしまいそうな気がして、仕方なしに廃墟ビルの中に入った。
蔓はそのまま動き続け、ビルの周りを覆っているようだ。
どうして蔓が勝手に動いているのかは全くわからないが、放っておいたらビルごと覆われてしまいそうだった。それよりも早く建物の上を目指す必要がありそうだった。
仕方なしに目の前の階段を駆け上がる。容赦なく息は上がっていく。なんでこんなことしてるんだろう、なんでこんなところに入ってしまったんだろうと後悔が何度も頭をよぎる。しかし、何もしないわけにもいかなかった。体を動かしつつ思考はぐるぐる回りながら、最上階へ辿り着いた。
扉も何もなく、いきなり全面屋外フロアだった。
壁に体をもたれさせて少し休憩する。外に出るとしゅるしゅると蔓の動く音が小さく聞こえた。
よたよたと中央へ歩いていく。先ほど聞いた、獣のような雄たけびが聞こえてとっさに身を縮めた。しばらくそのままだったが、何も起こらなかったようなので、もう一度ビルの中央へ進み出た。
建物の下の方から、蔓が壁を作ってビルごと覆いつくそうとしているように見えた。前方を向くと、霧がかかった先に、上り階段がうっすらと見えた。
方向は間違えていなかった。理由はわからないが、通ってきたところに今までなかったものが出てきている…ということになるらしい。
小説やゲームの不思議な場所に紛れ込んでしまったようで、薄気味悪いものが背筋を這い上がった。
「おぉぉぉぉおおおぉぉぉん!」
不意に、後ろから、先ほどから聞こえていた獣のような声が聞こえた。
「なっ…!え、ちょ、どういう…」
後ろを振り返ると、真っ白な物体が見えた。
―全然、何かがいるような気配はなかったのに。
それは狼のような口を持ち、ライオンのようなたてがみを持ち、四肢は太く荒く、獣と表現するにはぴったりだったか、具体的に何かということは一切わからない。
目に相当するだろう部分は空洞のように見える。
最も際立っていたのは、その体から先端が丸い何かが「生えている」ことだった。生えているその丸は時折人の顔のようなものを浮かび上がらせては消えている。
「な、なんなんだよ、これ…!」
獣が一歩踏み出す。次の瞬間、ものすごいスピードで自分に突っ込んできた。
反射的に顔を両手で覆う。風が体の周りを通り過ぎて行った感触がした。
そしてその次、横っ腹に強く引っ張られたような、強い衝撃を受けた。また次、今度は浮遊しているような感覚がした。
随分長い間飛ばされているような気がした。目を開いても、白い霧がかかっていて何も見えない。
そのまま気が遠くなり、意識を失った。
*************************************************
「…おいっ!いたぞ!」
誰かの声で、はっと気づく。今まで意識を飛ばしていたらしい。
「お、お前、何してんだよ!?大丈夫か!?」また別の人間の声がする。
だんだんはっきりしてきた意識が、救急車のサイレンの音を捉えた。
何かにもたれて座っているようだった。体を動かそうとしても、とても動ける気がしなかった。
「対象確認、対象確認、場所は公園内、北側!」
「名前、言える?」
「おいっ、何やってんだよお前、本当!どこ行ってたんだよ!」
救急隊員か誰かだろうか、腕のあたりを触っている感触がある。色々な人の声がする。
次第にどうでもよくなり、目を閉じた。
あれは、一体、なんだったんだろう―
とても、寂しい場所だった、気がする―
*************************************************
全身打撲、全治4週間。入院1週間。
それが、あいつの診断結果だった。発見時、ボロボロだった状態からすると信じられないくらい軽い診断だと思う。
一緒に帰った次の日、あいつは学校に来なかった。
初日はやっぱり体調でも悪いんかな、位しか思わなかった。
次の日も欠席で、やっぱり具合が悪いのかなと思った。
そしてまた次の日も来なくて、なんだか俺は薄気味悪くなった。
先生も、他の奴らも具合が悪いんだろうって言って全く気にしていなかったけど、俺は何かあったんじゃないかと思った。
何となく気になってあいつの家に行ってみたら、両親が蒼白状態で出てくるし、俺に何か知らないか聞いてくるし…いや、俺が知りたかったんだけど。
どうも、俺が一緒に帰った日から、あいつは家にいないらしいことがわかって
既に内密とはいえ捜索願は出ていて、混乱を防ぐために学校には言っていなかったようだ。学校が知っていたとしても、俺らのところにそんな情報降りてこなかったと思う。それこそ「混乱を防ぐため」。
そんなこと聞いちまったから、一応俺も探すことにして、家と学校の近く、あいつが寄りそうなところを訪れては来てないか聞き込みしてみたりしたけど、鳴かず飛ばず。
それで…思い出したんだ。
一緒に帰ったあの日、あいつはとても様子がおかしかった。
なんというか、とにかく変。そうとしか表現のしようがない。
授業中は上の空だし、体育では何もないところで転んだり、ありえないミスをする。宿題もほとんど忘れている。終いには公園の巨木を見て、何に見える?とか聞いてくる始末。
―公園の巨木。
あいつ、あそこにいるんじゃねぇか?あそこで、何かあったんじゃねぇの?
いることを願って、同時に変死体になんかなったりしていないことを祈って、行ってみたら…いたんだよ、あいつ。
巨木に寄りかかって、ボロボロの状態で。リュックみたいなもんが近くに落ちていた。
慌てて近くへ行って、とりあえず声をかけて揺さぶってみたけど、全く反応しねぇ。
呼吸を確認したら、息はあるみたいだった。
人生でこれほどパニックになったことなんてないんじゃねえかと思うくらい、慌てた。
すぐにスマホを取り出して救急車を呼ぼうとしたけど、手が震えてロック解除できないし、やっと解除できたと思っても番号押せねえの。
近くに公衆電話があったことを思い出して、物理キーでなんとか119を叩いて、救急車を呼んだ。自分の名前とか、聞かれた気がする。場所の説明もなんとかしたと思う。あいつのところに戻った。
相変わらず動いていなかった。眠っているようにも見えるけど、そうでないようにも見えた。
どのくらい経ったのか、すぐにかはわからないけれど、救急車がやってきて、俺はあいつから引き剥がされた。
そうこうしているうちに両親がやってきて、何か色々言っていたけれど…そこからは、よく覚えてねえ。俺もショックがでかかったんだよ。
念のためと俺も医者にかかった。心的外傷症候群、PTSDとかいうの?になってないか念のためしばらく通院することになるらしい。正直面倒くせえ。確かに発見したときは驚いたし焦ったし、しばらく夢に見たけどな。
何かあった、としか思えねぇ。
3日も不在で、ボロボロになって帰ってきて、それでいて「何もわからない」って、どういうことだよ。
みんなに心配かけやがって。捜査に来た警察も困ってんじゃねえか。
あいつが退院してから、自宅安静中に何度か会いに行った。
しばらくはなんだかぼんやりしているし、何があったか聞いても全く思い出せないようだったし、そもそもなんで公園なんかにいたのか、わからないとまで言いやがった。
公園の巨木の話をしたら、あれは巨木だろう?それ以外に何かあるのか?ととぼける始末。お前が聞いてきたんだよと言っても全く信じない。お前が俺に聞いてきたんだよ、本当。
途方に暮れていたある日、学校の図書館で、俺はあることが書いてある書物を、たまたま、見つけた。
なんで俺みたいのが図書館にいたかって、それは先生の用事で本を返しに来たっていうだけだったんだ。…俺は、図書館に詰めるなんてガラじゃねえし。
「この辺りには、大きな木がある。人によって見える大きさは異なる不思議な木だ。巨木という人もいるし、細い木という人もいる。」
ここで本のページが終わっていて、なんとなしに次のページをめくったんだ。
「建物があるという人もいるし、穴があるように見える人もいる。反対に、全く見えないという人もいる。見えない人は問題ない。問題は見える人で、かつ建物や穴といった、中に入れそうなものが見えた人だ。」
「そのまま特に何もしなければ問題はないが、入ってしまう人がいる。入ったら最後、戻ることはないという。また、時が経つとその人自体がなかったことになり、あるところから社会から抹消されていく。風化されていく。」
末恐ろしくなって、本を閉じた。
「忘れられたもの」
というタイトルだった。
もしかして、あいつは、こんな感じで、あの木ではない何か、が見えていたのか?
急ぎ足で図書館の用事を済ませ、あいつの家へ見舞に行った。明日から登校するらしい。怪我の治りは悪くないようだった。
回復するにつれて、あいつの様子は元通りになっていった。失踪前の変な感じも全く感じなくなっていた。
そこであの話をもう一度してみたけれど、やはり公園の巨木だろう?で話にならない。あんまりするとこっちが変な奴扱いになりそうで、それ以上は突っ込めなかった。
明日、学校で会おうぜと話をして、家を出る。
あの小説の一節にあるようなことが、実際に、あいつの身に起きたのではないか。自分が知らない間に、ずっと起きていたのではないか。
俺らが知らないだけで、社会から抹殺されて、風化していくから、認識できないだけではないのか?
つい、足は公園に向いていた。
あいつを見つけた、あの場所に向かっていた。
そこで俺が見たものは―